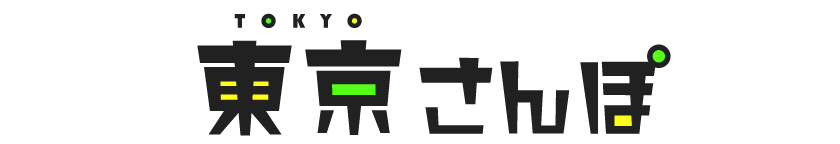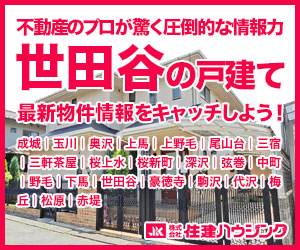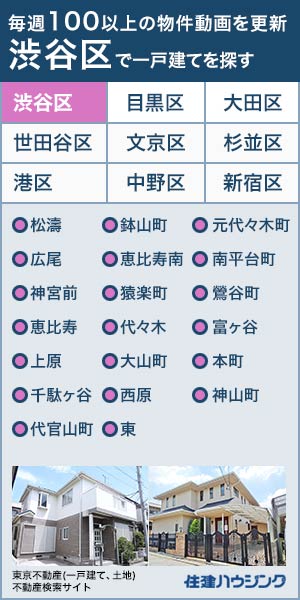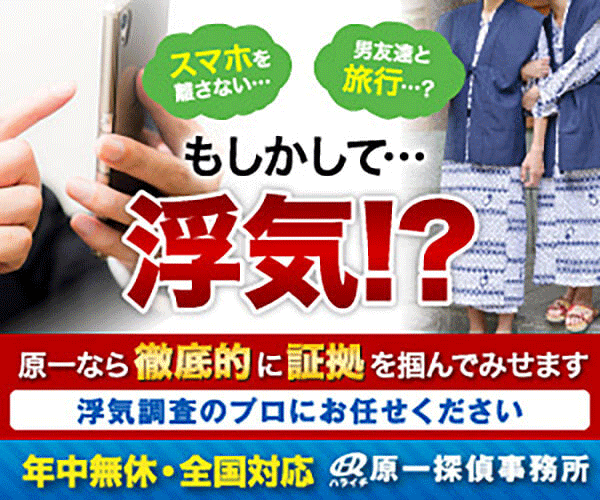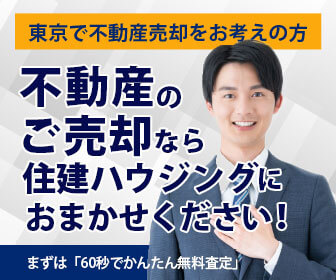目次
広尾の鼠塚とは?その歴史的背景
鼠塚が建てられた経緯
広尾の祥雲寺にある「鼠塚」は、明治時代末期にペストが流行した際、感染源とされたネズミたちを供養するために建てられた動物慰霊碑です。明治33年(1900年)、東京でペストが猛威を振るい、多くのネズミが駆除されました。その犠牲となったネズミたちの霊を慰めるため、明治35年(1902年)に建立されました。関西のペスト拡大を受け、東京市は鼠一匹を五錢で引取る買取策を開始。捕鼠専門業者が現れ「鼠成金」も生まれた。約2年間の捕獲数385万匹、買取費用は8万5千円。日露戦役を見越し「耳当て」の材料集めだったと後に流言も飛んだ。関東大震災で交番の鼠容器が喪失し廃止。広尾祥雲寺に供養塔鼠塚が伝わる pic.twitter.com/ipUMTwnzRh
— 敗者の歴史に光あれ (@wlxPRcrhlQC8Fw1) April 26, 2020
碑に刻まれた詩とその意味
鼠塚の裏側には、「数知れぬ 鼠もさぞや うかぶらむ この石塚の 重き恵みに」という歌が彫られています。この詩は、駆除されたネズミたちへの感謝と供養の気持ちを表しています。当時の人々は、疫病から解放された喜びとともに、その犠牲となった命への敬意を忘れなかったことがうかがえます。祥雲寺と広尾エリアの歴史
祥雲寺の由緒ある背景
祥雲寺は寛永6年(1629年)に創建され、初代福岡藩主・黒田長政公を祀るために建立されました。境内には江戸時代から続く大名家の墓地が並び、東京都渋谷区の文化財にも指定されています。また、東京大空襲を免れた本堂や、美しい庭園も見どころです。祥雲寺
— 北向き地蔵 (@KITAMUKIJIZO) February 21, 2025
東京都渋谷区広尾
元和9年(1623)筑前福岡藩主の黒田忠之が父黒田長政の菩提を弔うため赤坂溜池の屋敷内に建立したと伝わります。臨済宗大徳寺派の寺院で本尊は釈迦牟尼仏。開山は龍岳宗劉和尚。寛文8年(1668)現在地へ移転しました。境内には黒田長政の墓や鼠塚があります。 pic.twitter.com/M5jGzyYt1e
広尾エリアと武家屋敷の名残
広尾は江戸時代、武家屋敷が立ち並ぶ閑静な地域でした。現在では高級住宅街として知られる一方で、祥雲寺や鼠塚など歴史的なスポットも点在しています。こうした場所を訪れることで、広尾の過去と現在が融合した独特の魅力を感じることができます。鼠塚が伝える教訓と現代へのメッセージ
疫病との戦いと供養文化
鼠塚は、疫病との戦いにおいて犠牲となった命への感謝と供養の象徴です。ペストという恐ろしい感染症を克服するため、多くの命が犠牲になりました。その歴史を振り返ることで、人間社会がどのようにして困難を乗り越えてきたかを学ぶことができます。渋谷区広尾 祥雲寺にある鼠塚
— 鳥居 (@shinmeitorii1) July 5, 2020
明治32年から数年間にかけ、ペスト流行を抑えるため、防疫処置として殺処分されたネズミの供養塔 pic.twitter.com/ltDhBqaIL7
現代における鼠塚の意義
現代ではペストは過去の病気となりましたが、鼠塚は命への尊重や自然との共生について考えるきっかけを与えてくれます。この碑を見ることで、人間だけでなくすべての生き物に対する敬意や感謝の心を育むことができるでしょう。>> 広尾周辺の不動産(一戸建て・マンション・土地・事業用物件)を探す