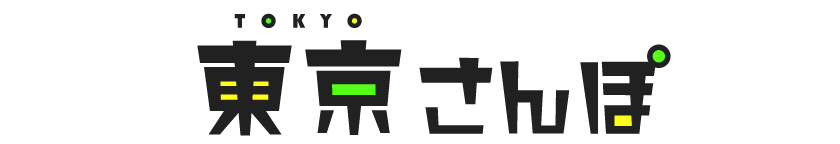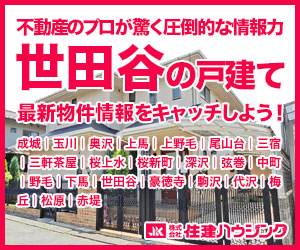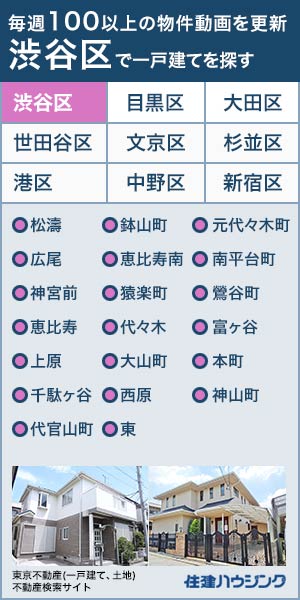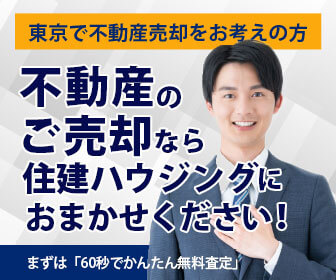江戸時代のペットには、現代と同じく犬や猫が多く飼われていました。特に町全体で面倒を見る「町犬」文化が特徴的で、愛犬家たちは犬を家族同然に大切にしていました。一方で、犬猫以外にも金魚や小鳥、虫、さらには鷹や白いハツカネズミなど、多彩な動物たちが江戸っ子の心を癒しました。今回は、江戸の犬猫事情から他の人気ペットについて詳しくご紹介します。
目次
庶民に愛された忠犬とネズミ退治の猫
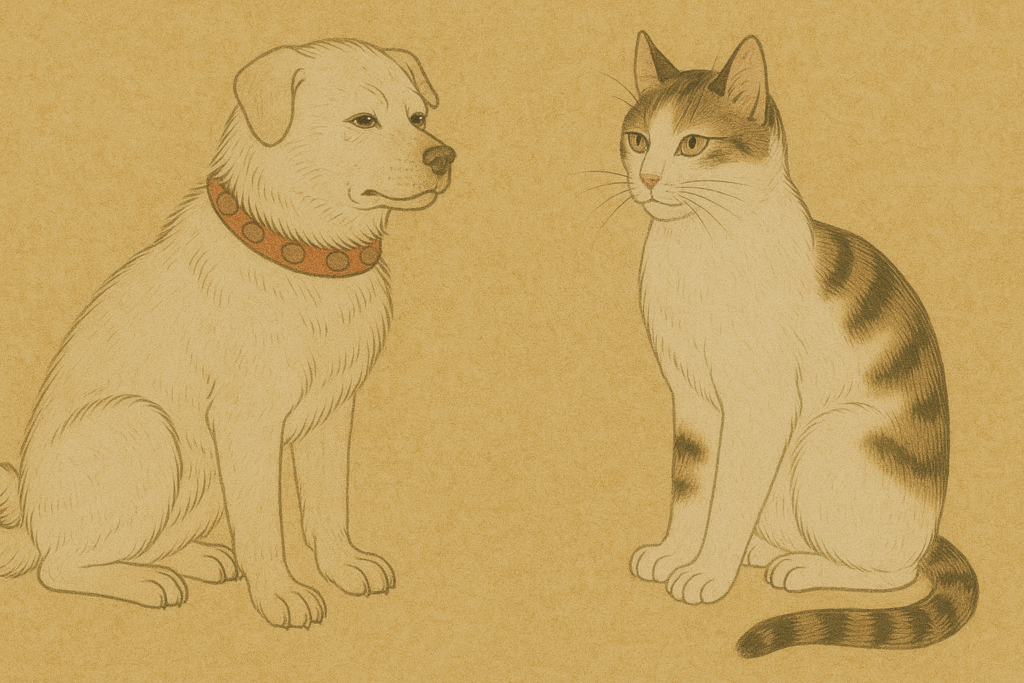
町犬文化と犬の暮らし
江戸の犬は、個人だけでなく町全体で世話をする「町犬」として多くの地域で見られました。幕府も殺処分を避け、動物を大切にする風潮が根付いていたため、犬たちは人々に愛されていました。日本橋の朝市の浮世絵にも犬への思いやりが描かれており、犬は江戸の暮らしに溶け込んでいました。徳川五代将軍・綱吉の時代には大規模な犬の保護屋敷が設けられるなど、社会的にも重視されていました。
江戸の猫とネズミ対策
猫はネズミよけとして重宝される一方、愛玩動物としても人気がありました。江戸末期には猫の絵や書籍も数多く発行され、その存在は江戸文化の中に浸透していました。鼠害対策は町の安全と生活の一部であり、猫の飼育は日常の知恵でもありました。
犬猫以外の江戸の人気ペット動物
金魚の大流行:両国・本所の金魚養殖
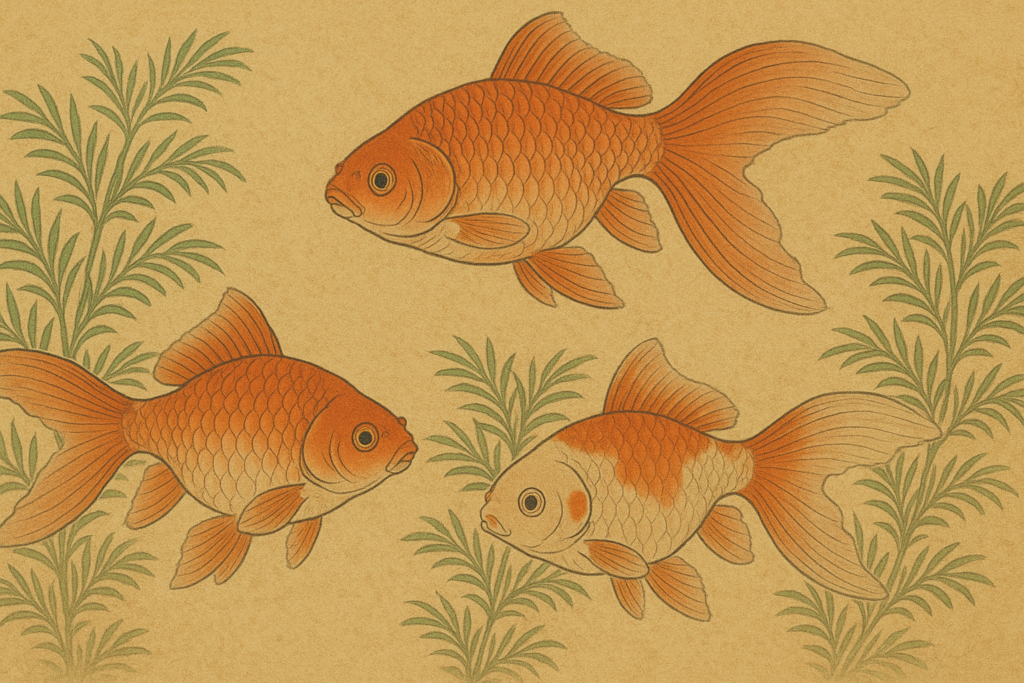
金魚は江戸時代に庶民の間で非常に人気を博しました。両国や本所(現在の墨田区周辺)で盛んだった金魚養殖は、夏の風物詩となり、商店街や祭りで金魚すくいが楽しまれました。美しいガラス鉢や陶器製の鉢が使われ、まるで現代のアクアリウムのように愛されていました。この地域では今日でも金魚の展示会や祭りが開催され、金魚を愛でる文化が色濃く残っています。浅草や隅田川周辺の街には、昔ながらの金魚すくいを楽しめる屋台や店舗があり、観光客や地元の人々に人気です。こうした金魚文化は「江戸の夏の風物詩」として、現代の東京においても根付いています。
小鳥の飼育:スズメから舶来のインコまで

スズメや鶯、ウグイスのような小鳥は庭先や屋内で籠に入れて飼われ、鳴き声を楽しむ風流な文化がありました。特に「鳥合わせ」という鳴き声を競う遊びも流行し、浅草や日本橋では鳥屋が賑わいました。異国から輸入されたオウムやインコも上流階級で飼育され、珍しいペットとして珍重されました。
虫のペット文化:鈴虫とコオロギの音色で涼を楽しむ
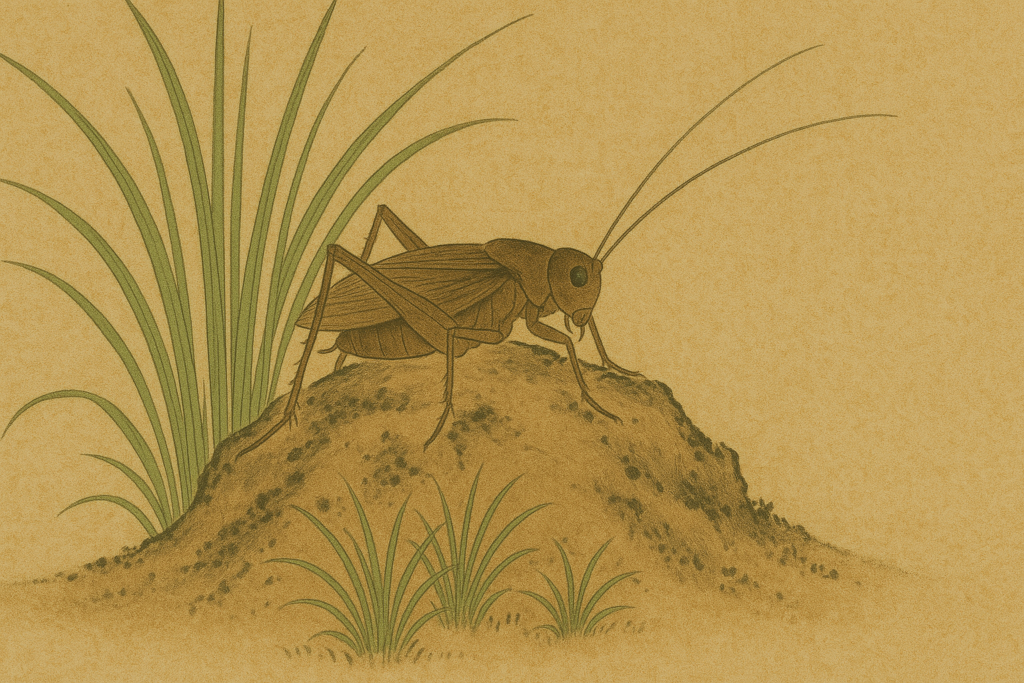
夏から秋にかけては鈴虫やコオロギなどの虫を籠で飼い、その鳴き声を家の中で楽しむ文化が庶民に浸透していました。虫売りの店が浅草や上野で賑わい、虫の鳴き声が秋の風情の象徴となっていました。虫飼育は今の音楽や自然音鑑賞と通じる楽しみだったのです。
江戸特有のペットたち
愛される小動物白いハツカネズミ

江戸時代の庶民の間では、特に白いハツカネズミが好まれ、小鳥よりも人気があったと伝えられています。見た目の可愛らしさと縁起の良さから、遊郭や裕福な町人の家でも飼育されました。
武士文化の象徴「鷹狩り」と鷹の飼育

武士階級は鷹を飼い、「鷹狩り」を嗜んでいました。幕府が指定した鷹場が目黒や世田谷にあり、これらの地名にその名残が今も残ります。鷹は武士の威厳と精神の象徴とされ、ペットとしても最高級の扱いを受けました。現在の下目黒は、かつての丘陵地帯で、鷹匠たちが技を磨いた歴史が伝わります。目黒区では文化財として鷹狩りにまつわる文書や史跡が保存されており、地域の祭りやイベントでも鷹狩りの伝承が継承されています。目黒不動尊などの歴史的スポットも、この鷹狩り文化と深く関わっていて、武士の嗜みであった鷹が地域文化の一部として息づいています。
ペットと共にあった江戸の暮らしと文化
江戸では犬や猫が最もポピュラーなペットでしたが、それ以外にも金魚、小鳥、虫、白いハツカネズミ、鷹など多様な動物が愛されていました。これらのペットは江戸の住環境や庶民文化を反映しており、現代東京の墨田区や台東区、目黒区など各所で当時のペット文化の名残が感じられます。動物と共に暮らす江戸っ子たちの情緒豊かな生活は、今日の東京にも続く文化的な遺産と言えるでしょう。