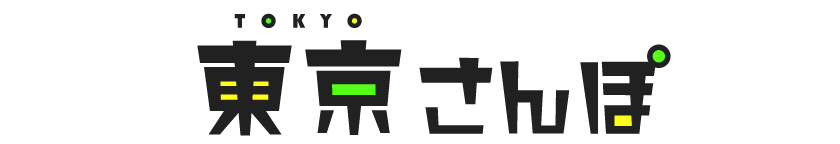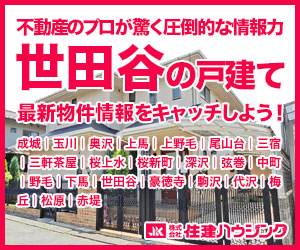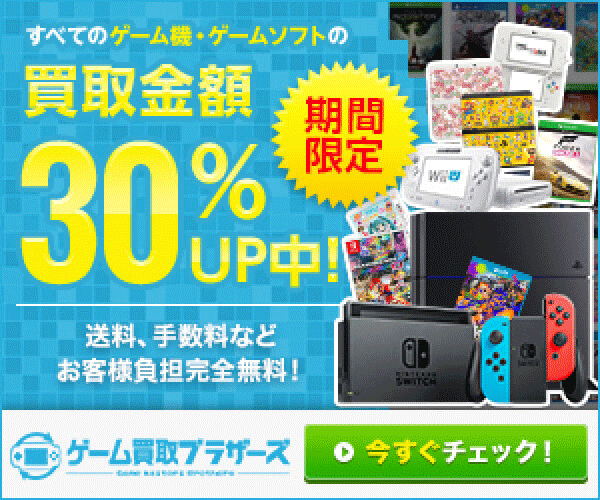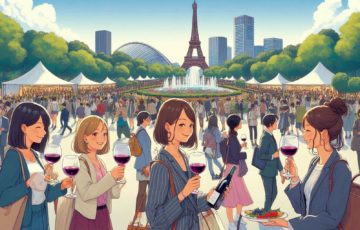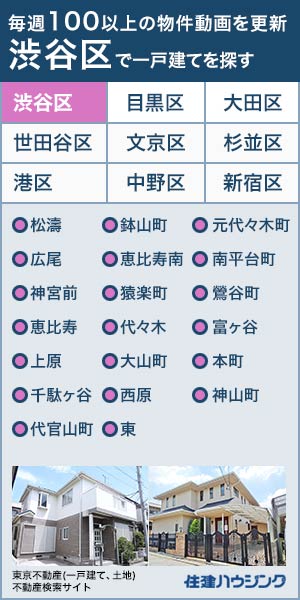JR山手線とJR総武線が交差する秋葉原駅周辺は電気街として有名です。
しかし、電気街の大部分は千代田区外神田と佐久間町に集中しています。
では 、駅の名前になっている「秋葉原」とはどこから付いたのでしょう?
幕末まで、今の秋葉原あたりには火除地があり、そこに秋葉神社(鎮火・防 火の神として、古来より篤く信仰され、各地にあります)を祭りました。
その広場が「あきばがはら」とか「あきばっぱら」と呼ばれていたそうです。
この呼び名が駅名になりました。
今でも地元では「あきはばら」でななく「あきばはら」が正しいと言う人もいるようです。